
道徳教育NEWS
日本教科書が発信する
教育ニュース
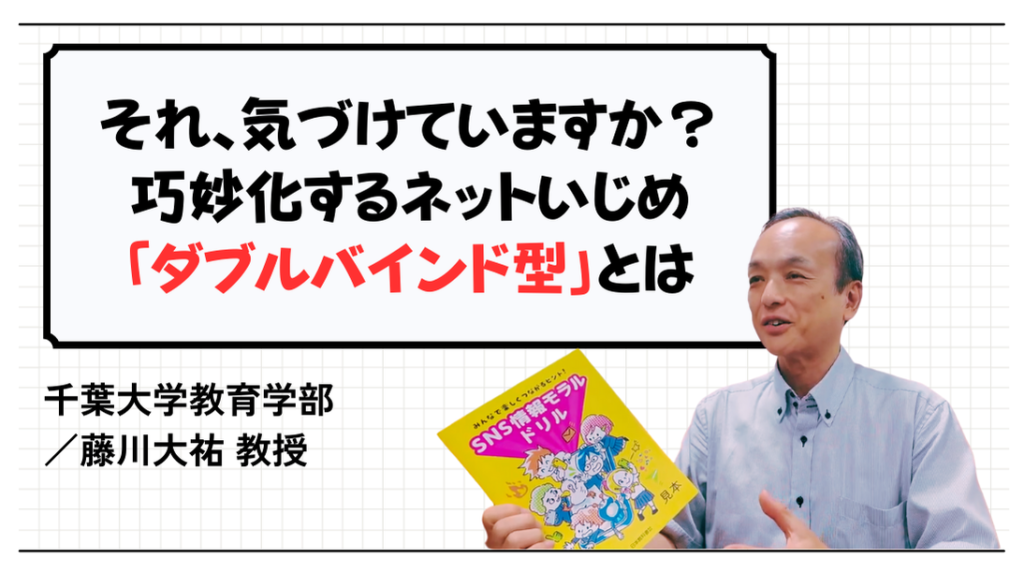
GIGAスクール構想の推進やコロナ禍を経て、子どもたちのデジタル活用は新たな段階へと進みました。もはや「ネットを使わせない」という選択肢はなく、「当たり前にある中でどう付き合うか」が問われる時代になっています。しかしその裏で、子どもたちのネットトラブルはより巧妙化し、大人の目には見えにくい形で進行しているといわれます。
こうした現状について、情報教育の専門家である千葉大学の藤川大祐教授に話を聞きました。現代のネットいじめの実態、教育現場での対処法、そして急速に普及するAIと教育の未来について、教育者は今どのような視点を持つべきなのでしょうか。
巧妙化するネットいじめ――見えない「ダブルバインド」の脅威
近年、中学校を中心に最も問題となっているのが、いじめかどうか判別しにくい「曖昧ないじめ」です。その典型例を、私は「ダブルバインド型いじめ」と呼んでいます。これは、LINEのステータスメッセージなどに、誰のことか特定できない形で「消えればいいのに」「うざい」といった悪口を書き込む手口です。
書かれた側は自分のことだと分かっていても、名指しされていないため被害を訴えにくいという特徴があります。「私のこと?」と聞いても「気のせいじゃない?」と言われれば、さらに傷つくことになります。これは、「あなたを苦しめる」というメッセージと、「あなたとは関係ないのだから苦しむ必要はない」という矛盾したメッセージを同時に発する「二重拘束(ダブルバインド)」状態であり、被害者を精神的に追い詰めてしまうのです。
この種のいじめは、いつも4人組でいるのに3人だけの写真をSNSのプロフィールに掲載するなど、スマートフォンの普及に伴い多様化しています。こうした行為は、された側が苦痛を感じていれば、いじめ防止対策推進法の定義上、明確にいじめとなります。私たち大人は、このような現代特有のいじめの形が存在することをまず認識する必要があります。
「教える」から「共に考える」へ――道徳授業で築くセーフティネット
こうした巧妙ないじめは、教員が自力で発見することが極めて困難です。いじめ認知件数の約8割は、アンケートや被害者側からの相談によって発覚しており、教員が発見するケースは2割に過ぎません。したがって、私が最も重要だと考えるのは、いじめを発見しようとすること以上に、子どもたちが「相談しやすい環境」をいかに作るか、という点です。
そのために中心的な役割を果たすのが「道徳」の授業です。授業の中で具体的な事例を取り上げ、「された側が苦痛なら、それは法律上いじめである」という共通認識をクラス全体で形成しておくことが、被害の申告へのハードルを下げると考えています。
しかし、既存の教科書だけでは、常に変化するネットの問題に対応しきれない側面もあります。新しい内容へのアップデートには限界があり、いじめ問題に割けるページ数も限られています。現場の先生方からは「自分のクラスで起きている問題に、ぴったりの教材が見つからない」という声も少なくありません。そこで今回、そうした現場のニーズに応えるため、私自身が監修に携わり、教科書を補ってより実践的な議論を促すための新しい副教材(SNS情報モラルドリル)を制作しました。
こうしたツールも活用しながら、いじめの問題に絶対的な正解はないという前提に立ち、生徒と「一緒に考える」というスタンスで授業に臨んでいただきたいのです。多様な意見を出し合い、対話する授業こそが、生徒たちの視野を広げ、いじめ問題の本質を考えさせるきっかけとなります。
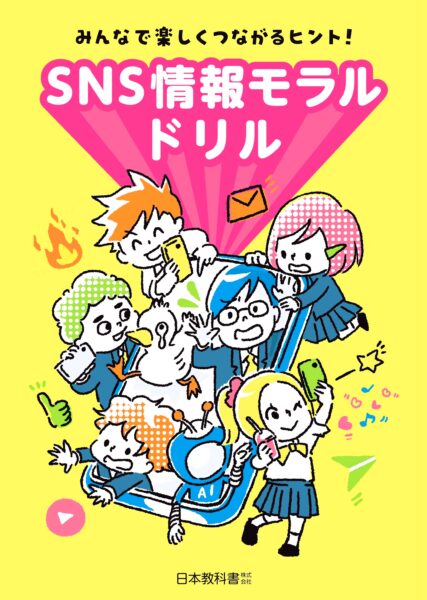 SNS情報モラルドリル
SNS情報モラルドリル
B5判・本文24ページ・オールカラー 定価330円(本体300円)
※全ページの紙面サンプルが閲覧、ダウンロードいただけます
AIは学習のパートナーか?――教育格差を生まないための向き合い方
ネットいじめと並ぶ現代の大きなテーマが、生成AIと学習の関係です。生成AIは、人間の歴史上かつてなかったほどの「物知りなパートナー」であり、探究学習の方法を相談したり、自分が書いた文章への意見を求めたりと、AIは生徒一人ひとりの学習を深める強力なツールとなり得ます。これまで一人では行き詰まりがちだった学習を、AIとの対話によって止めずに進められる点は、計り知れないメリットです。
その一方で、学習意欲がなく「勉強をやらされている」と感じている生徒にとっては、単に課題をこなすための道具になりかねません。これが、多くの方が懸念する思考力や学習意欲の低下による教育格差の拡大に繋がります。この問題に向き合うためには、「AIがあるのになぜ人は学ぶのか」といった根源的な問いを、道徳の時間などで生徒と共に考えることが、これまで以上に重要になるでしょう。
私が期待するのは、AIが「学習に悩む生徒の相談相手」となる可能性です。「なぜ数学を勉強するの?」「翻訳機があるのに、なぜ英語を?」といった、教員にはぶつけにくい素朴な疑問を、AIは否定せずに受け止め、根気強く対話してくれます。このような対話を通じて、生徒が自ら学ぶ意味を見出すきっかけを掴めるかもしれません。
もはや、単純な知識を問う学習の意味は薄れています。これからの教育で問われるのは、AIを「道具」として主体的に使いこなし、いかに深い探究ができるか、という点に尽きるのです。
変わりゆく「距離感」と教育者の役割
新しいメディアの登場は、人々の「距離感」を大きく変えます。インターネットや生成AIは、まさに現代における距離感の変革者です。私たち大人が、自分が若かった頃の感覚のままでいると、今の子どもたちの感覚を理解し間違えてしまいます。
先生方には、ご自身の「距離感」を意識してほしいのです。ネットの向こうの情報や人々との距離、AIが膨大なデータを一瞬で示す時間的な距離。これらが昔とどう違うのかを意識することが、子どもたちを理解する第一歩となります。子どもたちがこれから生きていく社会は、ものすごいスピードで情報を扱っています。その社会に彼らをどう送り出すか、という視点で教育を考えていく必要があるのです。
藤川大祐プロフィール
千葉大学教育学部教授。千葉大学教育学部学部長、元千葉大学教育学部附属中学校校長。メディアリテラシー、ディベート、環境、数学、アーティストや企業との連携授業など、さまざまな分野の新しい授業づくりに取り組む。著書に『考えよう!話しあおう!これからの情報モラル』シリーズ(2022年/偕成社)、『教師が知らない「子どものスマホ・SNS」新常識』(2021年/教育開発研究所)など多数。
インタビュー動画はこちら