
道徳教育NEWS
日本教科書が発信する
教育ニュース
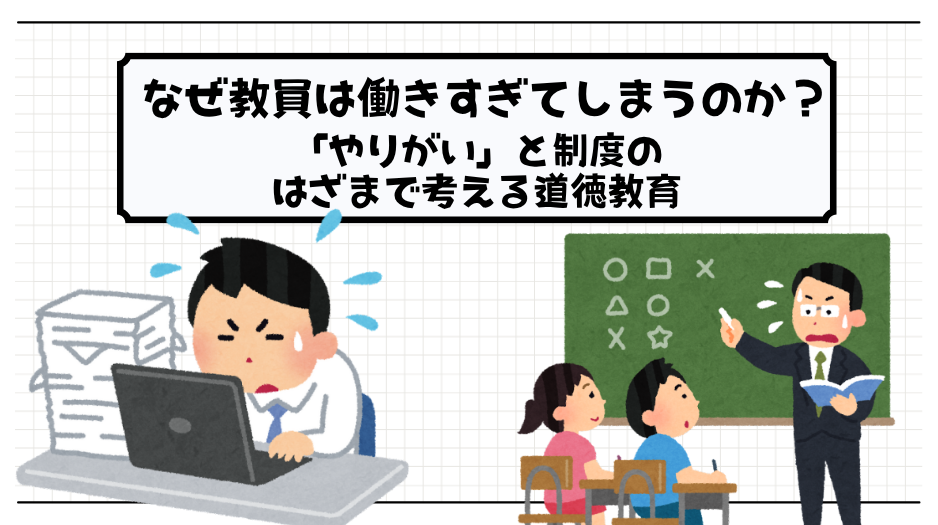
2025年5月14日、教員の働き方改革に関する大きな転機が訪れました。衆議院文部科学委員会において、「給特法」(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)の改正案が可決され、教職調整額を現行の月給4%から段階的に10%へ引き上げる方針が示されました。さらに、教員の時間外勤務を月平均30時間程度に抑える目標や、公立中学校での35人学級の実現に向けた施策も法案に盛り込まれました。
こうした制度改正は、教員の処遇改善と長時間労働の是正を目的としています。しかし、現場の教員からは「業務は減らず、むしろ時間管理が厳しくなっただけ」「やりがい搾取の構造は変わっていないのでは」といった声も根強く聞かれます。なぜ、教員はこれほどまでに働きすぎてしまうのでしょうか。この問いを出発点に、制度、業務実態、社会的期待、そして教育の本質にまで踏み込みながら、道徳教育との接続を探っていきます。
制度が固定化した「無限の労働」
教員の長時間労働は、個人の努力や職場の風土だけでなく、制度的な構造に深く根ざしています。給特法は、教員の時間外勤務に対して残業代を支払う代わりに、月給の4%(改正後は10%)を一律に上乗せする「教職調整額」を定めています。この制度は、教員の勤務が時間で区切りにくいという特殊性を前提としたものでしたが、結果として「どれだけ働いても追加報酬がない」構造を半世紀以上にわたり固定化してきました。
今回の法改正では、調整額の引き上げに加え、勤務時間の上限設定や学級規模の縮小、教育委員会に対する業務量管理計画の策定義務など、組織的なマネジメント体制の強化も図られています。しかし、制度が変わったからといって、現場の働き方が即座に変わるわけではありません。むしろ、「教員は時間外労働を前提とした職業である」という認識が社会に根づいてしまっていることが、改革の実効性を阻む一因となっています。
教育の名のもとに肥大化する業務
教員の仕事は「授業をすること」だけではありません。むしろ、授業以外の業務が日々の大半を占めているのが現実です。たとえば、部活動の指導・引率、保護者対応、校務分掌、行事準備、ICT機器の管理、地域・行政との連携業務など、教育活動とは直接関係のない「周辺業務」が膨大に存在しています。
これらの業務は、「教育の質向上」や「学校の信頼性確保」という名目で教員に課されてきましたが、実際には「サービス的業務」が多く含まれています。近年では、保護者や地域からの「顧客的な期待」が高まり、教員が「教育の専門職」ではなく「対人サービス業」として扱われる傾向も強まっています。SNS上での学校対応への批判や、即時対応を求める保護者の声は、教員の心理的負担をさらに増幅させています。
「子どものために」という思いが、制度の不備や社会の過剰な期待を補う手段として利用されてしまう──これが「やりがい搾取」と呼ばれる構造の本質です。個人の善意や使命感が、教育システム全体の「不足」を埋めるために吸収され、その価値が個人に還元されないまま消費されていく。この構造が、教員の働きすぎを生む根本的な要因となっています。
社会の「働き方改革」と子どもたちの未来
教員の働き方改革は、社会全体の「働き方改革」の流れの中で、最も遅れていた領域の一つです。企業ではすでに、長時間労働の是正、テレワークの導入、ジョブ型雇用への移行など、働き方の見直しが進んでいます。こうした改革は、単なる労働条件の改善にとどまらず、「働くことの意味」や「仕事と人生の関係性」を問い直す動きでもあります。
教員の改革がこの流れの最後尾に位置していることは、教育現場が社会の変化に対してどれほど保守的であったかを示すと同時に、今後の教育が果たすべき役割の大きさを物語っています。つまり、教員自身が「働くことの価値」や「働き方の選択肢」を見直すことで、子どもたちに新しい働き方のモデルを提示することができるのです。
子どもたちは、将来必ず社会に出て働く存在です。そのとき、働くことを「苦役」や「義務」として捉えるのか、それとも「自己実現」や「社会とのつながり」として捉えるのかによって、人生の質は大きく変わります。だからこそ、今の教育現場で起きている働き方改革は、子どもたちの未来の働き方に直結する重要なテーマなのです。
道徳教育で「働くことの価値」をどう教えるか
このような視点から、道徳教育において「働くことの価値」をどのように教えるべきかを考えてみたいと思います。学習指導要領では、「勤労」や「公共の精神」といった項目が道徳の重要な柱として位置づけられています。これらは、単に「働くことは大切だ」と教えるだけでなく、「なぜ働くのか」「働くことで何を得るのか」「社会にどう貢献するのか」といった根源的な問いを扱うことが求められています。
教員の働き方改革を題材にすることで、子どもたちにとっても身近でリアルな教材となります。たとえば、「先生たちはなぜそんなに忙しいのか」「働きすぎるとどんなことが起きるのか」「やりがいと健康のバランスはどうあるべきか」といった問いを通じて、働くことの多面的な価値や課題を考えることができます。
こうした学びは、将来の職業選択や社会参加において重要な価値観の土台となります。自分の働き方が、他者の生活や社会の持続可能性にどう関わっているのか──そうした視点を持つことは、これからの時代を生きる子どもたちにとって不可欠です。
教育現場から問い直す「なぜ教員は働きすぎてしまうのか」
ここで、冒頭の問いに立ち戻ってみましょう。なぜ教員は働きすぎてしまうのでしょうか。その答えは、制度の不備、業務の肥大化、そして「やりがい」による自己犠牲の構造が複雑に絡み合っているからです。そしてその背景には、社会が「働くこと」に対してどのような価値を置いているかという根本的な問いが横たわっています。
教員の働き方改革は、単なる労働条件の改善ではなく、「働くことの意味…とは何か」を社会全体で問い直す契機となるべきです。そしてその問いは、未来を担う子どもたちにこそ、しっかりと伝えていかなければなりません。
道徳教育の中で、「勤労」や「公共の精神」といった学習項目を通じて、働くことの喜びと責任、やりがいと限界、個人の幸福と社会の持続可能性をどう両立させるか──そうした問いを子どもたちとともに考えることが、今の教育現場に求められているのです。
そしてその出発点は、教員自身が「なぜ自分は働きすぎてしまうのか」という問いに向き合い、制度と文化の両面からその構造を見つめ直すことにあります。教員が自らの働き方を問い直す姿勢こそが、子どもたちにとって最もリアルで力強い「働くことの価値」の教材となるのです。
【参照】
【日本教科書編集部】