
道徳教育NEWS
日本教科書が発信する
教育ニュース
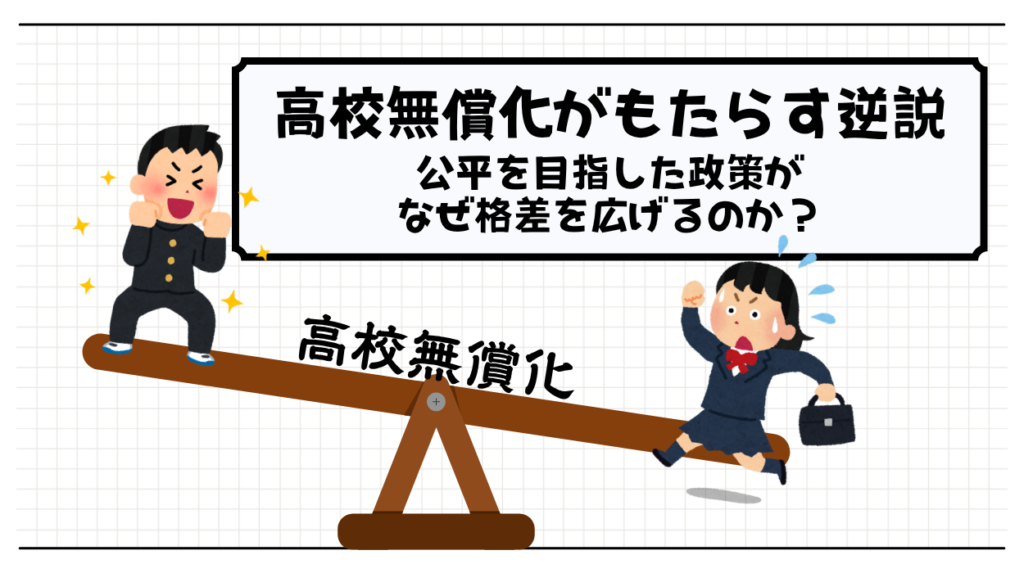
教育の「平等」はどこまで届いたのか
高校授業料の実質無償化が進み、2025年度には「子どもが3人以上いる家庭なら、年収800万円近くでも私立高校の授業料が全額支給される」という制度が導入されます。これは、経済的な理由で進学を断念することのない社会を目指し、教育機会の平等を保障するという理念のもとに進められてきた政策です。「すべての子どもに、等しく教育のチャンスを」というスローガンは、多くの人々の共感を得てきました。
しかし、実際の学校現場では、こうした理想と現実とのギャップに悩む声も上がっています。「結局、情報や資源にアクセスできる家庭ほど制度を上手に使いこなし、より有利な進学や教育環境を得ているのではないか」──そんな懸念が、制度が充実するにつれてむしろ強まっているのです。結果として、制度の恩恵が一様には行き渡らず、教育格差がより可視化されてしまっているという皮肉な現実が立ち現れています。
「無償化」が生んだ見えない壁
一見「公平」の象徴として受け止められがちな高校授業料の無償化政策ですが、その副作用として最も注目されるのが「私立高校人気の加速」です。授業料が公立と私立で同じくらいになるならば、保護者はより良質な教育環境、設備、進学実績などを求めて、私立を選びやすくなります。実際に、文部科学省のデータを見ても近年、私立高校の志願者数は右肩上がりで、その一方で公立高校は入学する生徒が定員に満たない学校が少しずつ増えています。
この状況は、お金の心配が減って「自由に学校を選べる時代が来た」とも言えますが、同時に資本の論理が教育に強く介入することを意味します。つまり、授業料が等しくなれば、相対的に「魅力ある学校」が選ばれ、「そうでない学校」──とくに公立高校──は生徒が集まらなくなります。結果として、一部の公立校では先生が足りなくなったり、お金が回らなくなったりして、教育の質が落ちる心配が出てきており、私立と公立の格差がさらに広がるという負のスパイラルに陥るではないかという懸念が広がっています。
もちろん、理想としては競争を通じて全ての学校の質が向上することが期待されます。しかし、学校は会社ではありません。経営戦略も宣伝のためのお金も少ない公立校が、設備も自由度も高い私立校と同じ土俵で“選ばれる側”として戦うのは難しい現実があります。
このように、無償化政策は教育機会の「平等」をある程度実現したものの、その結果として導かれるのは必ずしも「公正」や「公平」ではありません。むしろ、教育の質や進路格差という形で、別の不公平を生み出してしまっている現実があります。
受験の低年齢化と広がる格差
私立高校の人気が高まり、入試の倍率が上がったことで、もう一つ深刻な問題が生まれています。それは、受験がどんどん低年齢化しているという現実です。
前述のとおり、私立校人気が高まり、難関校の倍率は5倍を超えるような状況となっています。つまり以前より受験の難易度が上がっており、保護者たちは、より早い段階から準備を始めるようになりました。
特に目立つのが、中高一貫校への中学受験の加熱です。都立中高一貫校の倍率は4倍前後で推移しており、私立中学受験でも、大手受験情報サイトのデータによると2025年度の首都圏中学入試の実質倍率は平均で約3.7倍と過去最高レベルに達しました。これに伴い、小学4年生や5年生から、週に何日も塾に通う生徒が急増しています。
この動きは、中学校の先生方にとって大きな課題を突きつけています。受験塾に通う生徒と通っていない生徒との間で、すでに小学校高学年の段階で学力差や学習意欲の差が大きくなり、中学校に入学してからの授業の進め方に悩む先生が増えているのです。学習塾に通うには高額な費用がかかりますから、この「早期からの受験競争」は、家庭の経済力や情報リテラシーが、子どもの教育機会に直接影響するという、新たな教育格差を強く生み出していると言わざるを得ません。無償化政策が、皮肉にも「塾に通えるか」という新たな格差の壁を生んでしまっているのです。
「平等」ではなく「公正」か?──理想と現実のギャップ
教育における「平等」とは、全ての子どもが「同じもの」を受けられる状態を指します。現在の制度は、経済的な障壁を取り除くことによって「機会の平等」を保障しようという意図のもとに設計されています。しかしその結果として、制度の利用をめぐる競争が生まれ、むしろ格差が広がってしまっている側面もあります。つまり、「平等なスタートライン」が整備されたことで、より早く、より遠くへ進める家庭とそうでない家庭との間で、「結果の格差」が拡大しているのです。この構造をどう捉えるか、そしてそれを是とするか否かについては、今後の社会的議論が必要とされるでしょう。
たとえ制度が「機会の平等」を整えていたとしても、家庭の文化的背景、情報へのアクセス、教育に対する価値観の違いが、その後の行動や選択に大きな差を生んでしまいます。その結果、制度を「活かせる家庭」と「そうでない家庭」のあいだで、成果や経験に開きが出てくるのは避けがたい現実です。
制度が用意するのは“入り口”の平等であり、そこから先の学びや成長の道のりは、家庭や地域社会、学校文化といった多様な環境要因に委ねられます。だからこそ、教育政策は金銭的支援に加えて、文化的・心理的な障壁に対する多層的な視点をもつことが必要です。ただし、それらすべてを制度で包摂しきろうとするのではなく、多様な主体が役割を分担しながら、地域や社会全体として長期的に支えていくことが現実的な方向性だと言えるでしょう。
道徳の授業で考える──「本当の公平」ってなんだろう?
「機会の平等」を目指した制度が、結果として格差を助長している、この状況を理解する上で、経済学者アマルティア・センの「ケイパビリティ(潜在能力)」の概念が大きな示唆を与えてくれます。センは、単に制度としての“機会”が整っていることだけでは不十分であり、人が実際にそれを活かせる自由や力(ケイパビリティ)を持っているかどうかが重要だと主張しました。
ケイパビリティとは、単なる選択肢の有無ではなく、それを活かして「なりたい自分になれる力」「実際に行動を選び取る自由」を指します。つまり、制度上は同じ教育機会が与えられていても、その選択を行動に移せるかどうかは、個々の人間が持つ資源や支援、環境に大きく依存するということです。
この視点は、ジョン・ロールズが提唱した「公正としての正義(正義論)」──すなわち、誰もが平等な基本的自由と公正な機会を与えられるべきだという考え方──に対する補完または修正として語られます。ロールズはスタートラインの平等を整えることを重視しましたが、センは「実際に走る力が人によって異なる」ことに注目し、平等を評価するなら「達成できることの実質的な自由」に着目すべきだとしたのです。
このような理論的背景は、本来は高校の「倫理」や「公共」で扱われる内容ですが、道徳の授業でも、生徒の関心や現実に即したかたちで先取り的に取り上げることができます。特に高校無償化の問題は、生徒自身の進路に直結しており、現実味がありながらも抽象的な価値観に触れる良い題材です。制度の恩恵をどう活かすか、あるいは制度の限界をどう補うかといった議論を通して、「公正」や「自由」の意味を考える道徳的探究へと導くことができるでしょう。
たとえば、生徒たちには次のような問いを投げかけてみるとよいでしょう。
「授業料が無料になって、すべての人に“チャンス”が与えられたとする。でも、そのチャンスを本当に“使える”かどうかは、何によって決まるのだろう?」
「同じ制度のもとでも、自分の力を発揮できる人とそうでない人がいるのはなぜ? その違いは『本人の努力』だけで説明できるだろうか?」
「本当に必要なのは“平等なスタートライン”だけなのか? “走り切る力”や“支える仕組み”についても考えるとしたら、どんな工夫や支援がありえるだろう?」
これらの問いには明確な正解はありませんが、生徒たちが自分とは異なる状況に置かれた人の視点に立ち、「誰が取り残されているのか」「どんな条件が“公正な社会”をつくるのか」を考え始めることこそ、道徳的な思考の出発点です。制度を「公平」にするとはどういうことか──その問いを対話のなかで共有する時間こそが、今の道徳授業に求められているのではないでしょうか。
参考文献・資料
- 文部科学省「高等学校等就学支援金制度について」https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/detail/1411300.htm
- 文部科学省「令和5年度学校基本調査(速報値)」https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00400101&tstat=000001011528&cycle=7&tclass1=000001011531
- 首都圏模試センター「2025年中学入試予測資料」https://www.syutoken-mosi.co.jp/
【日本教科書編集部】