
道徳教育NEWS
日本教科書が発信する
教育ニュース
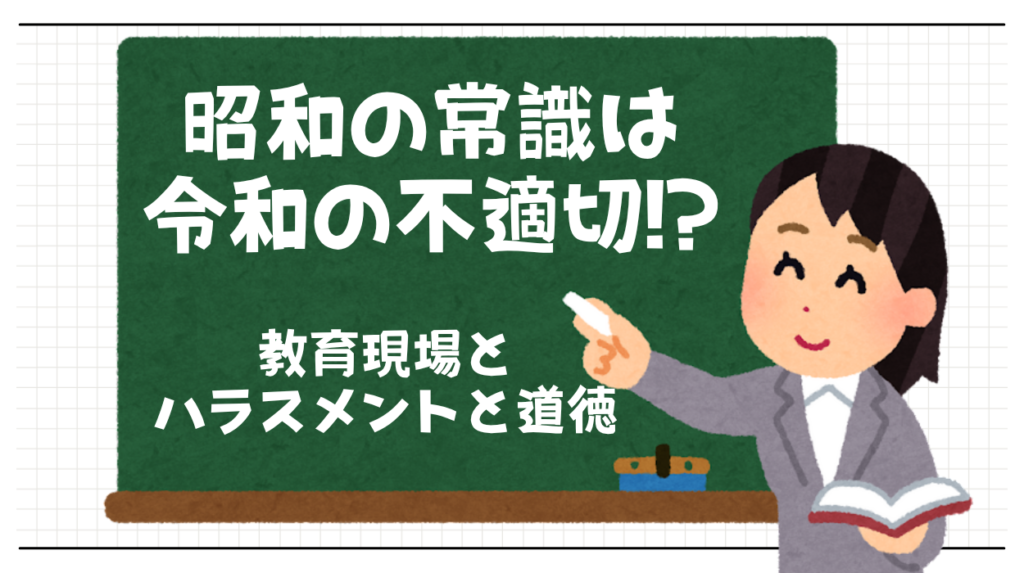
昭和の教育現場で培われた常識を持つ教員が、現在の令和の学校に足を踏み入れたら、そのギャップに驚きを隠せないかもしれません。かつて良しとされた指導法は、今や時代錯誤とされ、場合によっては法に触れる行為とさえ捉えられます。これは単なる教育システムの変更ではなく、社会全体の倫理観が大きく転換した結果です。本稿では、教育現場における昭和と令和の価値観の対立に焦点を当て、その背景にある社会的な課題と、現代が直面する教育のジレンマを深掘りします。
指導から暴力へ
体罰に対する価値観の転換
【昭和】 昭和の教育現場では、「愛のムチ」という言葉に象徴されるように、教育的指導の一環として身体的な罰が一定程度容認されていました。授業態度や部活動における「気合を入れる」という名目のもと、教員による体罰は問題視されにくい風潮がありました。それは、子の教育に関して学校や教員に全幅の信頼を寄せるという、当時の社会的なコンセンサスに支えられていた側面もあります。
たとえば、昭和の終わり頃に小中学校を過ごした筆者の世代にとっては、体罰は日常的なものでした。小学3年生のとき、美術の授業で黄色いブルドーザーを緑色で描いただけで、担任の教員から「ふざけるな!」と強烈な平手打ちを受け、頭がくらくらして頬にしばらくあざが残るほどのひどい体罰を経験しました。当時、母親は心配はしてくれたものの、学校への抗議などはしませんでした。こうしたエピソードは、当時の社会が体罰を教育の一部として受け入れていた現実を如実に示しています。
【令和】 令和の現在において、体罰は「いかなる理由があろうとも許されない暴力」であるというのが絶対的な原則です。2020年に施行された改正児童虐待防止法では、親権者による体罰も禁止され、学校現場ではさらに厳格な対応が求められます。厚生労働省は『体罰等によらない子育てのために』(2020年)と題した資料で、体罰が子どもの成長に与える悪影響について啓発しています。暴言や威圧的な態度も心理的虐待と見なされるなど、人権意識の高まりを背景に、指導は対話と相互理解を基本とする形へと大きくシフトしました。
聖職からサービス業へ?
保護者・地域との関係性の変化
【昭和】 昭和の教員は高い教養を持つ「聖職者」として社会的に敬意を払われる存在でした。地域社会においても、教員は知的階層が上の人物として敬意を払われ、時には地域の相談役を務めるなど、単なる学校の職員を超えた役割を担っていました。家庭訪問の際には、保護者が教員を自宅に招き、丁重にもてなし、「うちの子をどうかよろしくお願いします」と、子どもの教育全般を学校や教員に一任するような姿勢が一般的でした。学校行事においても、保護者は教員の指示に従い、積極的に学校運営に口を出すことは稀でした。教員と家庭の間には、良くも悪くも明確な序列意識が存在していました。
【令和】 令和の保護者は「教育サービスの利用者」としての側面を強め、学校や教員に対して具体的な要望や意見を主張することが一般的になりました。例えば、子どもの学校生活や学習内容について疑問があれば、すぐに学校に連絡して説明を求めたり、SNSを通じて学校の対応について意見を発信したりするケースも珍しくありません。一部には「モンスターペアレント」という言葉に代表されるような過度な要求もありますが、この言葉が「新語・流行語大賞」にノミネートされた2007年には、すでに保護者と学校の関係性の変化が社会的に認識され始めていたことがうかがえます。全体として、学校や教員には保護者への丁寧な説明責任が強く求められるようになっています。保護者会でも、教員が一方的に話すのではなく、質疑応答の時間が長く設けられたり、PTA活動も多様なニーズに対応した形へと変化しています。
寛容から警戒へ
ハラスメント意識とDEIの浸透
【昭和】 昭和の時代は、教員が生徒の容姿について言及したり、親しみを込めて身体に触れたりすることが、特に問題視されない風潮がありました。例えば、男子生徒の髪型を「丸刈りにしろ」と指導したり、女子生徒のスカート丈を「短い」と注意したりといった、現代ではプライバシーや人権侵害とみなされかねない指導も日常的に見られました。ジェンダーに関する配慮も乏しく、特定の性別に対する固定観念に基づいた言動や、無意識のうちに生徒を傷つける発言があったことは否定できません。
【令和】 令和の現在、セクシャルハラスメントやパワーハラスメントに対する社会の厳しい視線は、教育現場にも浸透しています。生徒個人のプライバシーや人格を尊重するため、教員が生徒の身体に不必要に触れることは厳しく禁じられ、異性の生徒と二人きりになる状況を避ける、呼び方は「さん」付けに統一するなど、細やかな配慮が求められます。
さらに、近年ではDEI(Diversity, Equity, and Inclusion:多様性、公平性、包摂性)の概念が教育現場にも広がりを見せています。例えば、性自認と異なる制服の選択を認めたり(文部科学省のガイドライン等にも示唆)、LGBTQ+の当事者を招いた講演会を実施したり、発達障害のある生徒への個別配慮を重視したりするなど、多様な背景を持つ子どもたち一人ひとりが安心して学べる環境づくりが進められています。これは生徒を守る上で極めて重要ですが、その一方で、教員側には過度な萎縮を生み、生徒との間に必要以上の距離感が生まれているという指摘もあります。
考察
揺れ動く倫理観と、これからの道徳教育
令和の教育現場における人権意識の向上やDEIの推進は、社会の成熟を示す大きな成果です。しかし、その急進的な変化に対する戸惑いや息苦しさが社会に渦巻いているのも事実です。その心理を巧みに捉え、世代を超えて反響を呼んだのが、テレビドラマ『不適切にもほどがある!』でした。視聴者は、昭和の主人公が放つ本音に、現代の過剰な「正しさ」への風刺としてカタルシスを感じたのです。
こうした変化への反動は、日本に限った現象ではありません。より大きなスケールで顕在化したのが、アメリカにおけるトランプ大統領の登場と根強い支持です。トランプ大統領は、多様な立場への配慮を求める「ポリティカル・コレクトネス(政治的正しさ)」やDEIの潮流に対し、連邦政府機関におけるDEIプログラムの終了を命じる大統領令に署名したり、民間企業に対してもDEIへの取り組みを停止するよう働きかけたりするなど、あえて既存の規範を破るような言動や政策を繰り返しました。これは、その厳格な適用に「息苦しさ」を感じていた層や、実力主義を重視する層からの強い共感を得て、リベラルな価値観の急進的な浸透に対する「バックラッシュ(揺り戻し)」として分析されています。バックラッシュとは、特定の社会運動や価値観の進展に対して、それに反対する勢力や保守的な価値観を持つ人々が反発し、元の状態に戻そうとする動きを指します。
このことは、私たちが絶対的で普遍的だと考えがちな「道徳」や「倫理」が、実は時代や社会状況によって大きく揺れ動く、相対的なものであることを強く示唆しています。昭和の「常識」が令和の「不適切」になるように、現在の令和の「常識」もまた、次の世代から見れば「不適切」と見なされる可能性を孕んでいます。
この事実を踏まえるならば、現代の学校における道徳教育のあり方そのものが、再考されるべきではないでしょうか。絶対的な一つの「正しい答え」を教え込むのではなく、道徳や倫理が時代とともに変化する相対的なものであるという前提に立ち、その是非について生徒自身が深く考える機会を提供すること。そして、多様な意見が対立する現代社会において、何をもって「より良い」と判断するのか、その判断基準をいかに形成していくのか、といった根源的な問いを生徒自身が探求する力を育むこと。これこそが、変動する社会を生き抜くために、これからの道徳教育が担うべき真の役割なのかもしれません。
【日本教科書編集部】