
道徳教育NEWS
日本教科書が発信する
教育ニュース
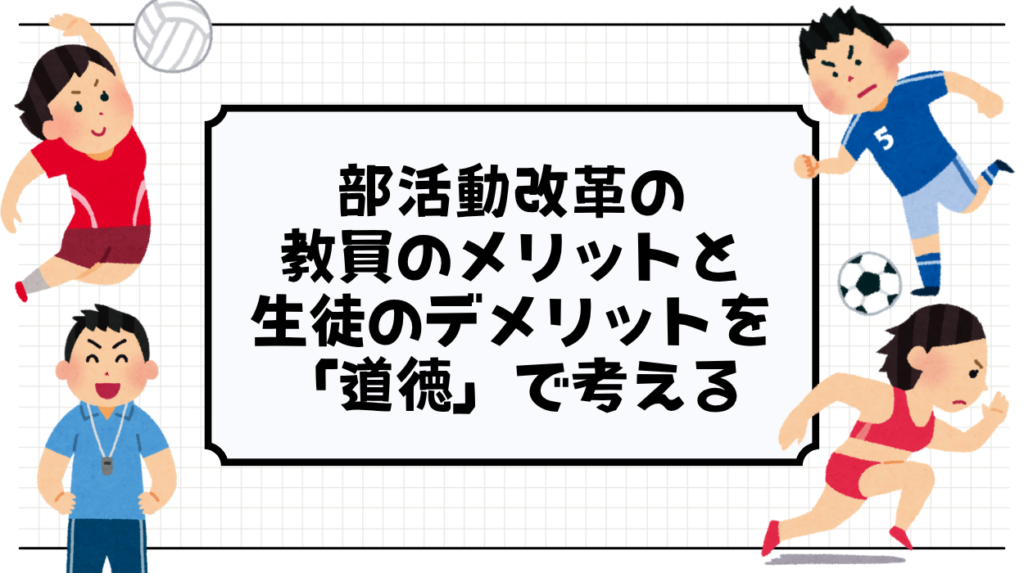
いま、中学校の部活動は大きな転換期を迎えています。教員の長時間労働是正という喫緊の課題に応えるため、「部活動の地域移行」が全国で急速に進められていますが、その実情は地域によって大きな差があり、思わぬ課題も浮上しています。先生方にとっては働き方改革の「特効薬」となる一方、生徒たちにとっては「部活動がなくなるかもしれない」「遠征費が家計を圧迫するかもしれない」といった「副作用」への不安が渦巻いています。
2025年5月16日には、文部科学省・スポーツ庁・文化庁の三庁合同で進めてきた「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」が、休日部活動を地域クラブに切り替える最終とりまとめを公表しました 。文書は「2026〜2031 年度を改革実行期間とし、2031 年度に休日部活動の地域展開を“全国原則実施”する」と明記 。あわせて①地域クラブ活動の認定制度、②十分な財政支援(会費上限の国基準)、③専門アドバイザーの派遣、④周知・広報――という四つの施策パッケージを示し、改革のゴールと工程表を国として“確定”させました 。
部活動の現場でこの改革の影響を最も直接に受けるのは、まさに中学生と彼らを指導する中学校教員です。両者が「当事者」として向き合える生きた教材であるからこそ、道徳の授業で公共政策を考える格好の題材になります。
本稿は、都市部と地方における部活動改革の実態を具体事例で照らしながら、この改革が私たちに突きつける〈公平性〉と〈公共性〉という道徳的問いを探ります。
都市と郊外で異なる「部活動改革」の現実
「来年度から、野球部を含むすべての部活動が地域クラブ〈KOBE◇KATSU〉に一本化されます」。神戸市のこの方針は、都市部で最も先行する“フル移行”モデルとして注目されています。少子化で休部が相次ぎ、顧問のなり手も減る──そんな現状を前に、市は「平日も休日も地域へ」という大胆な舵を切りました。クラブ運営費は市が補助し、月3,000円程度で参加できる仕組みを目標としています。
対照的に、千葉県印西市では、地域クラブ移行の青写真そのものがまだ描き切れていません。市教育委員会は2026年度9月に野球と女子バレーボールの2種目を休日のみクラブ化するモデル実証を計画していますが、指導者確保や費用負担の基準が定まらず、実施主体となる組織も未決定のため、スケジュールが後ろ倒しになる可能性が指摘されています。2024年に行った保護者アンケートでも「送迎が増える」「月謝が不透明」といった不安の声が過半数を占め、行政と地域が合意形成に苦戦しています。
先生の負担減 VS 生徒の活動機会―二つの視点
現行の中学校では、顧問が土日の引率に月10時間以上を費やしながら、時間外手当が支給されない無償労働が常態化しています。地域クラブ化は、教員が週末指導という拘束から解放され、週末を家庭や教材研究に充てられる点で異論はほとんどありません。
ところが生徒側から見ると、話は単純ではありません。神戸市のように都市部でクラブが乱立する地域では、「学校外コーチの専門的指導」「他校との合同チーム」といったメリットが前面に出ます。一方、印西市のようにクラブの受け皿が整わない地域では、そもそも活動場所や指導者が確保できず、休日の練習そのものが縮小する恐れが現実味を帯びています。つまり、“先生のメリット”と“生徒のデメリット”がぶつかる地域もあるのです。
地域差は宿命か、それとも──
地方自治は「地域の実情に応じた教育」を保障する一方、財政力や人口規模の違いをくっきり映し出します。神戸市は市単独でクラブ運営費を補助し、月3,000円程度の会費目標を掲げていますが、印西市では体育館の照明や白線引き直しなど施設利用に伴う諸経費をクラブ側が負担せざるを得ず、保護者負担が膨らみがちです。国は今年度中に“受益者負担の上限”を示すとしていますが、公共施設の無料開放や指導者への謝金補助をどこまで自治体が肩代わりできるかで、活動の質は大きく開くでしょう。
こうした地域差を「仕方ない」と片づけるのか、それとも新たな公共サービスとして再設計するのか──そこに問いがあります。
道徳の授業で考える「部活動の未来」
部活動の地域移行は、まさに道徳の授業で取り組むべき「公共的課題」です。先生の働き方や生徒の活動機会、地域間の格差といった、複雑な利害関係が絡み合うこの問題を考えることは、子どもたちが現代社会を生き抜く上で不可欠な、多角的な視点や公共心を育む絶好の機会となります。
では、どのような授業が想定されるでしょうか。
【公正・公平性を考える問い】
「先生の部活動の負担が減ることは良いことだけど、もし自分の部活動がなくなったり、活動が減ったりしたらどう感じるだろう?」
「神戸市と印西市の事例から、地域によって部活動の状況が大きく違うのはなぜだろう?それは『仕方ない』ことだろうか?」
「部活動は『学校が無料で提供すべきもの』だろうか?それとも『費用を払ってでも参加すべきもの』だろうか?」
このような問いから、生徒に問題を「自分ごと」として捉えさせ、公正・公平の観点から問題を捉え、多角的に思考するきっかけとなります。
【自分たちの地域の現実を調べる活動】
「私たちの住む自治体は、部活動の地域移行についてどのような方針を出しているだろう?」「地域のスポーツ施設や文化施設は、部活動の受け皿になれるだろうか?」といった問いを立て、生徒が実際に各自治体の教育委員会のウェブサイトや広報資料、地域のスポーツ団体や文化施設の情報を調べる活動を取り入れることができます 。
調べた結果をクラスで共有し、自分たちの地域の「強み」や「課題」を具体的に洗い出すことで、遠い地域の話ではなく、「自分たちの身の回り」の問題として捉える視点を養います。この活動を通じて、生徒は地域の公共の精神や協働の重要性を肌で感じ、責任感と主体性を育むことができるでしょう。
地域の自治体関係者(教育委員会担当者など)や、実際に地域クラブで活動しているOB・OG、保護者などをゲストとして招き、現状や課題、期待について直接話を聞く機会を設けることも有効です。
【公共サービスのあり方を議論する】
部活動が「公共のサービス」として、どこまで平等に提供されるべきか、その費用を誰が負担すべきかといった、より踏み込んだ議論を展開します。
生徒を「市の担当者」「保護者代表」「部員代表」などの役割に分け、部活動の運営方針を話し合う模擬会議を行うことで、複雑な利害調整や合意形成の難しさを体験させることも考えられます。この議論は、よりよい社会の実現を目指す上で、一人ひとりがどのような役割を担い、責任を果たすべきかを考える機会となります。
おわりに
部活動の地域移行は、都市か地方かで“処方箋”が違う──。先生の働き方改革という“特効薬”が、生徒にとっては副作用を生むかもしれない。だからこそ、この現状を直視し、生徒自身が「自分の地域では何が足りないか、どう補えばいいか」を考える教材にする価値があります。
地方自治の原則は、地域ごとの多様な解を認める代わりに、格差という副産物も抱えます。その現実を踏まえながら、「誰にとっても納得できる部活動のかたち」を探す対話こそが、道徳の教室で取り組むべき公共的課題だと言えるでしょう。この複雑な社会課題を生徒と共に深く考察する経験は、彼らが未来の社会を担う市民として、困難な問題に対しても多角的に思考し、解決策を探る力を養う土台となるはずです。私たち教師の挑戦が、子どもたちの「生きる力」を育む確かな一歩となることを信じて、共にこの公共的課題に向き合っていきましょう。
【参考資料】
文部科学省「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議 最終とりまとめ」(2025.5.16)
神戸市教育委員会「KOBE◇KATSU 概要」
印西市教育委員会「部活動地域移行説明会資料」(2025.4)
印西市教育委員会「第3回部活動地域移行推進協議会 議事録」(2023.9.28)
【日本教科書編集部】