
道徳教育NEWS
日本教科書が発信する
教育ニュース
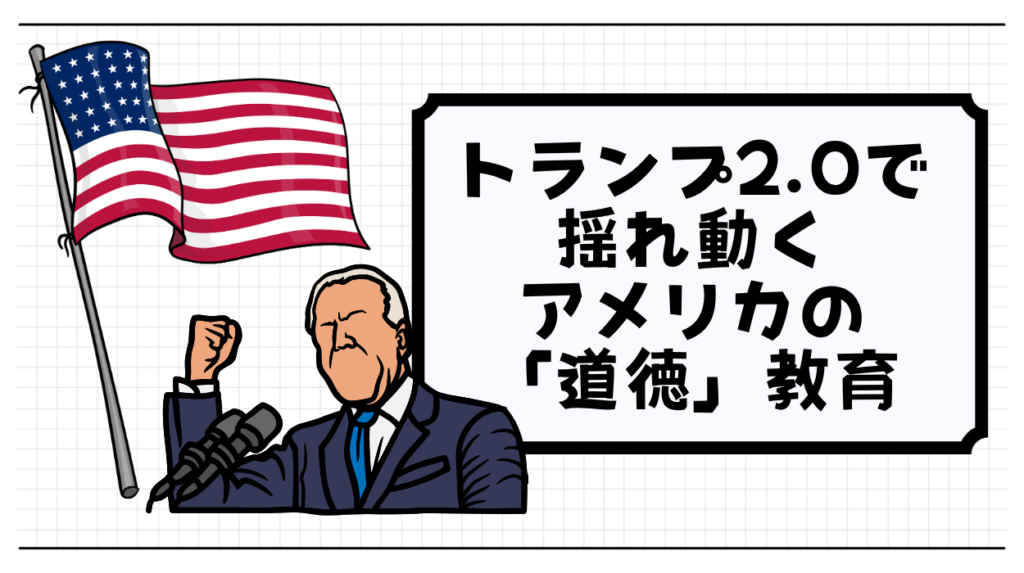
1 日本の「道徳」とアメリカの「SEL」はどう違うの?
日本の小中学校には週1時間の必修教科として〈道徳〉があります。授業ではいのちの大切さや思いやりを、物語や話し合いで学び、全国どこでもほぼ同じ内容が保障されています。アメリカでは道徳という科目はありませんが、その代わり、多くの州や学区がSEL(Social-Emotional Learning=社会・情動学習)という枠組みを使います 。SELは「自分の気持ちを知る」「友だちと協力する」「正しい判断をする」といった、社会性や情動の「スキル」習得を系統的に伸ばす学びで、ホームルームや週1コマの専用授業、そして英語や社会の時間にも溶け込ませる形で行われます 。
2024年の全米調査では、公立校の83%が何らかのSELプログラムを実施していました 。また50州のうち27州が幼稚園から高校まで通じたSELの州基準を持つと報じられています 。ところがこのSELが今、トランプ政権の政策により、大きな転換を迫られています。
2 トランプ2.0でアメリカの教育は大きく揺れている
2025年1月に発足したトランプ政権は、教育現場で使われる「人種差別」や「ジェンダー」についての教材を「過激な洗脳」と呼び、DEI(多様性・公平性・包括性)やSELを名指しで問題視する大統領令を相次いで出しました 。特に、アメリカの歴史における人種差別の現実をより深く扱う教材や、多様なジェンダーアイデンティティについて肯定的に扱う教材が問題視されたと考えられます。
教育省も3月に「SELが差別を隠れみに使われる場合がある」とする文書を公表し、連邦資金を受ける学校に対しプログラムの再点検を求めました 。こうした動きに呼応し、フロリダやテキサスなど保守色の強い18州は、SELや多様性研修を部分的に禁止・縮小する州法を可決しました 。これは、伝統的な価値観との衝突や、リベラルな思想が公教育に浸透することへの警戒感が背景にあると見られます。
一方、イリノイやマサチューセッツのようにSEL基準をむしろ強化する州もあり、全米で「推進」か「制限」かの二極化が起こっていると言われています 。
3 なぜこんな現象が起こっているのか
まず、アメリカでは「教育の決定権は州や学区が持つ」という仕組みが大きな前提にあります。連邦政府が「この授業はやめなさい」と言っても、最後に決めるのは現場の教育委員会なのです。
次に、近年は「子どもの教育内容を親が選ぶ権利」を主張するグループが力を持ち、授業で使う言葉ひとつがニュースやSNSで激しく批判されることが増えました 。これは、特定の思想に基づいた教育内容への反発や、公教育への不信感の高まりが背景にあると言えるでしょう。
さらにトランプ政権の発足後、連邦補助金は「読み書き計算と愛国教育を重視する学校」を優先する仕組みに改められ、SELを続けたい学区は「このプログラムによって学力が向上した」という具体的なデータを細部まで提出しなければ、資金を確保できなくなりました。こうした流れの結果、教員は余計なトラブルを避けるために教材を差し替えたり、授業の内容を変更せざるを得ない状況が各地で起きているのです 。
4 日本への影響はあるのか
教育行政が中央集権型の日本で、県ごとに授業内容が真っ二つに分かれるような事態は起こりにくいでしょう。しかし影響がまったくないとも言えません。
第一に、SEL由来のワークシートや評価ルーブリックは日本の道徳授業でも引用が増えており、例えば「感情を言葉にするワークシート」や「協力的な学びを評価するルーブリック」などが導入されています。アメリカ発の規制や批判は教材選びを慎重にさせる可能性があります。日本の教員は、海外の事例も参考にしつつ、教育内容が特定の思想に偏っていないか、多様な意見を持つ児童生徒に配慮しているか、といった点にこれまで以上に注意を払う必要があるでしょう。
第二に、SNSで授業内容が瞬時に広がる今の時代、授業で扱うテーマの説明責任は日本でも高まるでしょう 。特に多様性やジェンダーといった価値を教室で扱う際、特定の価値観を押し付けていると受け取られないための配慮、そして多様な意見を持つ児童生徒への対応が求められます。丁寧な根拠提示と対話の場づくりが欠かせません 。
おわりに
トランプ政権が示すのは、価値や感情を扱う授業が政治の風向き一つで揺れ動くという現実です。今、アメリカ社会は大きな変革期にあり、その波は経済や政治に留まらず、教育にも及んでいます 。戦後、日本の教育の基礎がアメリカの占領政府の指導のもと作られた歴史を顧みれば、日本もまた、その大きな流れと無関係ではいられないことは明らかでしょう。
道徳教育は社会の鏡です 。グローバル化と社会の多様化が進む中で、日本の教育現場でも価値観が揺れ動く場面は増えるかもしれません。例えば、外国籍の子どもの増加やジェンダーをめぐる議論など、新たな課題が日々生まれています。
だからこそ、これからの日本の教育に必要なのは、価値観がぶつかった瞬間に「なぜそう考えるのか」を対話で確かめ合う機会を、学校文化として根づかせることではないでしょうか。教室は小さな公共広場です。そこで子どもたちが異論に耳をふさがず、自分の言葉で折り合い点を探る経験を積めるかどうかが、分断が深まる世界で“次の分断を起こさない大人”を育てられるかどうかの分岐点になります。