
道徳教育NEWS
日本教科書が発信する
教育ニュース
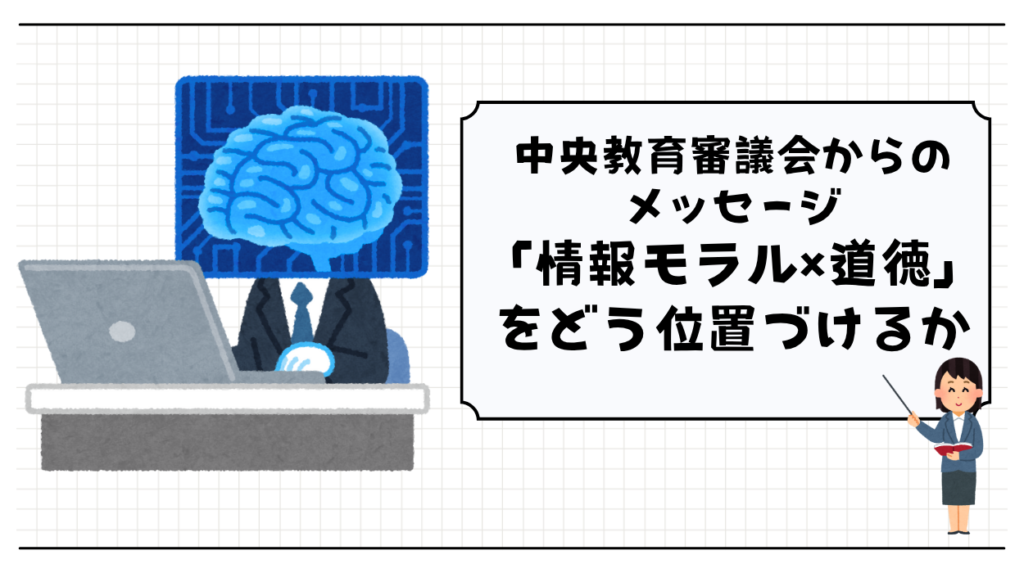
1 生成AI時代の「学び」をどう作り直すのか
2025年1月、中央教育審議会は次期学習指導要領の中間整理として『これまでの議論を踏まえた論点の整理』(以下、「論点整理」)を発表しました。この文書は、学校教育がこれから向き合うべき柱をはっきりと掲げています。第一に「子どもたちの情報活用能力を根本から高めること」。第二に「生成AIを含めた情報モラル・メディアリテラシー教育を強めること」です。その一方で、委員会は「ICTを使うこと自体が目的になってはいけない」とも強く注意を促しています(論点整理 p.13)。
実はこの警鐘は、生成AIの急速な発展を踏まえたものです。二〇二二年に公開されたChatGPTを皮切りに、AIの回答は驚くほど正確かつ高速になりました。たとえば最新モデルとされるGPT-4o miniは、汎用推論のテストで正答率八割近くを記録したと報じられています(SMSデータテック社解説記事)。「第二次世界大戦の原因は?」と質問すれば、年表も要因も影響も瞬時に返ってくる時代です。
こうした状況で、中教審は子どもたちに「単に答えを覚える学び」から一歩進んだ学びを求めています。資料には「他者を大切にし、多様な人と協力して社会の創り手になる子ども像」(p.6)が示されています。つまり知識そのものよりも、知識をどう判断し、どう行動につなげるかが重視されているのです。この「価値判断」と「責任ある行動」を育てる場として、特別の教科 道徳が再び脚光を浴びています。
2 学校現場に立ちはだかる二つの壁――「教師のリテラシー」と「ルールの未整備」
理想を実現するには、まず二つの大きな課題を乗り越える必要があります。ひとつめは教員側のリテラシー格差です。論点整理は「教師が必要な資質・能力を身に付けられる環境を実現することが不可欠である」(p.18)と書いています。しかし現場には、生成AIや最新SNSを使いこなす先生がいる一方、基本操作に不安を覚える先生も少なくありません。「生徒のほうが詳しい」と感じると、授業中に深い問いを投げることに戸惑いが生じるのが現実です。
もうひとつの課題は、運用ルールの不足と子どもたちとの温度差です。論点整理は「ICTの活用が目的化してはならない。学びの質を伴う活用方策を各学校で設計すべきだ」(p.13)と指摘しています。実際は忙しい日常の中で、ガイドライン作りまで手が回らない学校もあります。その間にも生徒はスマートフォンで動画編集をし、画像生成AIでアイコンを作り、深夜までチャットを続けています。こうした温度差が広がるほど、道徳の授業で語る「ルール」や「マナー」が現実味を失い、かえって生徒の反発を招きやすくなるのです。
3 道徳が向き合うべき三つの焦点――論点整理が示す具体的課題
ネットいじめ
論点整理では、情報モラル教育の例として「SNS上の誹謗中傷や個人情報の拡散」(p.27)を挙げています。実際、文部科学省が公表した令和5年度の調査では、いじめの認知件数が73万件を超え、SNSを通じたトラブルが大幅に増えたと報告されました。道徳の授業では、「既読スルーは傍観なのか、それとも配慮なのか」「スタンプや短い言葉でも暴力になり得るのか」といった問いを通して、公正さや思いやり、責任を子どもたち自身の問題として考えさせることが求められます。
生成AIの活用
論点整理は、「生成AIの利用を学びの質の向上に結びつけつつ、その限界とリスクを批判的に検討できる力を育成する」(p.29)と強調しています。授業では「AIが作ったレポートは自分の学びと呼べるのか」「もしAIの結果に偏りがあったとしたら、誰がその責任を負うのか」といった問いを立てます。こうした問いは、公平性や自律、責任という価値を多面的に考えるきっかけになります。教師は完璧な答えを用意する必要はありません。むしろ事前にAIが生成した文章や画像をいくつか用意し、そこに潜む問題点を生徒と一緒に探すだけでも、十分に深い対話が生まれます。
スマホ・ゲーム依存
論点整理は「学びの質を損なわない活用時間と生活時間のバランスを児童生徒自身が設計できるようにする」(p.30)と述べ、デジタル依存への目配りを促します。道徳授業では、生徒自身のスマホ使用時間やゲーム時間を振り返り、「便利なツールとうまく付き合うにはどうすればよいか」を話し合うことなどが考えられるでしょう。たとえば一日の利用時間を円グラフにして可視化すると、「思ったよりスマホに時間を使っている」と気づく生徒が多くいます。そこから「夜九時以降は通知を切る」「勉強の合間に五分だけSNSをチェックする」など、各自が実行可能なルールを決めて試し、次の時間に振り返るといった流れが効果的です。
これら三つの焦点はいずれも「正解」が一つではありません。だからこそ、子どもたちが互いの意見を聴き合い、価値観を揺さぶられながら、自分の答えを選び取る経験が大切になります。論点整理が求める「主体的・対話的で深い学び」は、まさにこうした時間の中で実現していくのです。
おわりに――AI時代を生き抜く「心の羅針盤」を育むために
中央教育審議会の論点整理は、生成AIとSNSが当たり前になった現代だからこそ、道徳科が担う役割をあらためて示しました。ネットいじめ、AI活用、スマホ依存という三つの課題は、子どもたちが毎日直面しているリアルなテーマです。教師はこれらの課題に「答え」を与えるのではなく、問いの投げ方や対話のつなぎ方を工夫し、子ども自身が価値を判断し、行動を選び取るプロセスを支える存在へとシフトしていく必要があります。
もちろん、教員リテラシーの差やガイドライン不足はすぐには解消しません。しかし、同じ教材を手にする仲間同士が学び合い、授業を少しずつ磨き続けることで、子どもたちは生成AI時代を生き抜く「心の羅針盤」を手に入れるはずです。
なお、日本教科書では、こうした学びを後押しする教材として『SNS情報モラルドリル』(仮題、2025年10月発刊予定)を準備しています。生成AIの光と影、SNSいじめの具体例、スマホ依存のセルフチェックなど、本稿で紹介した三つの焦点に沿った「問いと対話」の素材を多数収録する予定です。日々の道徳授業にぜひお役立てください。
【参考資料】
- 中央教育審議会「これまでの議論を踏まえた論点の整理」(2025年1月21日公表)
https://www.mext.go.jp/content/20250121-mxt_kyokasyo01-000039635_1.pdf - 文部科学省「令和五年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」ポイント版
https://www.mext.go.jp/content/20241031-mxt_jidou02-100002753_2_2.pdf
【日本教科書編集部】